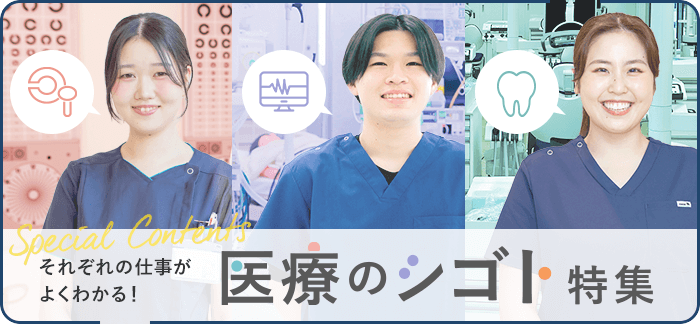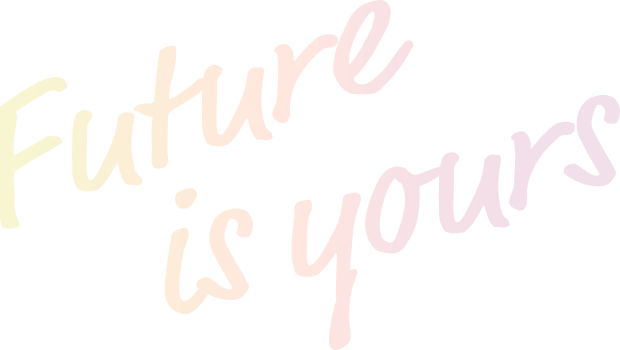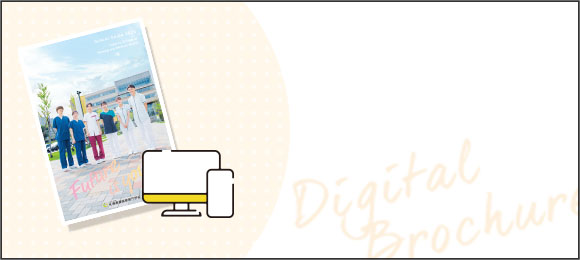医療の道に進もうと考えている皆さん、一口に「医療職」と言っても実際には様々な職種があり、どう違ってどの仕事が自分に向いているのか、なかなか判断できずにお困りではありませんか?
今回は、医療職の中でも「看護師」と「臨床工学技士」の違いを徹底解剖!
医療の現場でのお仕事内容はどう違うのか、またお互い現場ではどういう連携をしているのかまでご紹介します。
進路選びの参考にしてくださいね。
臨床工学技士の主な業務
| 業務内容 | 説明 |
| 人工呼吸器管理 | ICUなどで人工呼吸器の設定やトラブル対応 |
| 血液浄化(透析) | 血液透析・腹膜透析装置の操作と保守 |
| 心臓カテーテル室業務 | PCIなどの検査・治療中に機器操作・デバイス管理 |
| ペースメーカ管理 | 植込み後の作動確認や設定変更 |
| 医療機器管理 | 病院内の医療機器の点検・修理・貸出管理 |
| 人工心肺操作 | 心臓外科手術での体外循環装置の操作(専門教育を受けたCEのみ) |
看護師の主な業務
| 業務内容 | 説明 |
| バイタルサイン測定 | 体温・血圧・脈拍・呼吸などの観察と記録 |
| 投薬管理 | 医師の指示による薬の準備・投与・観察 |
| 清潔ケア・食事介助 | 入浴、排泄、食事の援助など日常生活の支援 |
| 医師の診療補助 | 採血、処置、検査の準備・補助 |
| 患者・家族支援 | 病気や入院への不安を軽減し、退院後の支援も含む |
| 急変時対応 | CPRや緊急対応の実施と医師への報告 |
⚠️ 共通点もあるが、アプローチが異なる
• ICUや手術室などでは協働することが多い
例)人工呼吸器管理では、設定・保守を臨床工学技士が、患者の状態管理を看護師が行います。
• 患者を守るという目的は共通
→ ただし「機器を通して支える臨床工学技士」「人に直接寄り添う看護師」という役割分担があります。
看護師から見た臨床工学技士の関わり方
✅ 一言でいうと…
「命を支える医療機器のプロフェッショナルであり、現場の安心を支える存在」

🏥 現場での具体的な関わり方(看護師目線)
| シーン | 看護師の立場 | 臨床工学技士との関係 |
| 人工呼吸器使用中の患者ケア | 患者のSpO₂低下や呼吸異常に気づく | 呼吸器のトラブルかどうか判断してもらい、調整を依頼 |
| 血液透析中の看護 | バイタル変化や体調の急変に対応 | 透析条件の確認・装置異常への即対応が頼れる |
| 手術室での準備 | 機器が使えるか不安、操作に慣れていない | 操作説明やスタンバイをしてくれるので安心 |
| 緊急時(心停止など) | 心電図や除細動器の準備が必要 | すばやく機器を操作、使い方をサポート |
| 医療機器に不慣れな新人指導 | 教えるのが難しい | 簡潔に説明・教育支援をしてくれる |

💬 看護師が抱く印象・評価
安心感がある:「困ったときに呼べば来てくれる」「自分では気づけない機器の不具合も見てくれる」
頼れる存在:「苦手な機械を丁寧に教えてくれる」「ミス防止にもつながる」
もっと関わりたい:「病棟にもっと来てくれると助かる」「情報共有の機会が増えると連携しやすい」
まとめ
臨床工学技士は、「機器の専門家」として、看護師にとって現場の安心と連携の要。
看護師と臨床工学技士は、「人」と「機器」の両面から患者を支えるチーム医療のパートナーなのです。
現場での声の掛け合い、情報共有、相互リスペクトが質の高い医療につながります。強い信頼関係で結ばれ、助け合う関係性ということですね。
どちらも医療の現場には必要不可欠な存在ですが、役割や働きが違います。どちらがより自分の目指す医療職に近いか、札幌看護医療専門学校で一緒に学びながら考えましょう^^